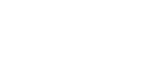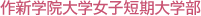- 【学生インタビュー】教員採用試験合格者インタビュー
- (最終更新日:2025/02/19)
-
2025年2月14日
令和7年度 公立学校教員採用試験において、人間文化学部 発達教育学科より13名(延べ人数)の合格者を輩出しました。発達教育学科では、少人数制の授業スタイルを重視しており、大学の教員と学生の距離がきわめて近く、きめ細やかな教育を実践しています。さらに、教職実践センターでは教員をめざす学生に学習の場を提供しています。
今回は合格者インタビュー第1弾として、合格者の中から3名の学生に、本学での学びや試験勉強について聞いてみました。
人間文化学部発達教育学科4年
・福島県公立小学校合格 熊木 翔悟さん
・栃木県公立小学校合格 佐藤 玲菜さん
・福島県公立小学校合格 山内 俊太朗さん
⇒発達教育学科の詳細は こちら
⇒教職をめざす学生へのサポート体制は こちら
福島県公立小学校合格
熊木 翔悟さん(栃木県立宇都宮南高等学校卒業)
-
教員を目指したきっかけを教えてください
中学生の頃の担任の先生の影響が大きいです。先生が楽しそうに授業をしている様子を見て、教師という仕事に興味を持ったことがきっかけです。将来は子どもに寄り添い、一人一人の学びを支えることができる教師になるため、日々の努力を怠らずに学び続けていきたいと思います。
合格に向けてどのような準備をしましたか?
本格的に準備を始めたのは、3年生になった頃です。複数の県の特色や、加点や受験資格といった試験の制度を調べ、自分がどの都道府県を受験するかを決めました。4年生になってからは、それぞれの県の特徴をもとに、とにかく過去問を解きました。
作新大での学びはどのように役立ちましたか?
私が特に合格につながったと感じているのは、現職の先生が講師を務める講義を受けることができたことです。現在も教育現場でご活躍されている先生方に教えていただくことで、私たちが小・中学生だった頃とは大きく変化した教育現場の実態を把握することができ、教員を目指す身として非常に有意義な学びとなりました。
後輩へのメッセージをお願いします
特筆すべきは、身近に教職に携わった先生方が多くいらっしゃることだと思います。悩んだ時にはすぐに相談でき、助言をいただける環境は学生にとって心強いものだと感じます。また、教職実践センターがあることも作大の良い学習支援だと思います。教育現場で実際に使用されている教科書がそろえられており、実習前の準備や大学の授業で活用できるため、実際の現場を意識した学習活動が可能になります。
栃木県公立小学校合格
佐藤 玲菜さん(本庄東高等学校卒業)
-
-
教員をめざすきっかけを教えてください
教員をやっている親戚が多い環境にいたため、小学生の頃から教員という仕事に何となく興味を持っていました。また、私の母校の小・中学校では教育実習生が毎年来ており、一緒に遊んだり実習生の授業を受けたりしていました。そして、実習生の先生方は私が悩んでいると、どんな時でも一緒に悩み、考えてくれました。先生方と過ごした1ヶ月がとても楽しかったことを今でも覚えています。
小学生の頃から、教員を目指す人の背中を見て育ち、私も教員になりたいと思いました。この経験や教育実習で実際に自分が学んだことを生かして、子どもたちの能力を最大限に生かし共に成長できる教員になりたいです。
合格に向けてどのような準備をしましたか?
1次試験の対策としては、大学1年生の頃から教員採用試験講座に参加したり、長期休暇を利用して、受験してみたい都道府県の過去問を解いたりしました。本格的に勉強を始めたのは3年生の春休みです。受験までの時間が少なかったので、過去問と2つの参考書を使い対策をしていました。苦手な数学と理科は、知人に解き方を教えてもらいました。国語は過去問を中心に、社会は参考書を中心に解きながら勉強しました。英語に関しては、出題年数が浅く、傾向が読みづらかったため、高校受験用のドリルを活用しました。
私は、教員採用試験の対策をしながらもアルバイトを続けたかったので、“スキマ時間(朝起きてから授業に行くまでの時間など)”を活用し、自宅や教職実践センターで勉強していました。朝イチは過去問を解く時間に充てていたのですが、実際の試験時間よりも10分短い時間で解くようにしていました。そのため、試験当日は見直しの時間を多くとることができました。また、「分かるまで問題を解く」というよりは「問題を見たら解き方を思い出せる」ということを意識しながら演習問題や過去問に取り組みました。そして、10分考えても分からない問題は先生や知人に聞くことを徹底しました。これが“分からない問題は飛ばしてどんどん問題を解く”という解き方の練習になりました。
2次試験の対策としては、教職実践センターの先生方と面接練習をしました。また、面接経験が豊富な友達に面接官役をやってもらったり、卒論担当の先生には“面接で合格するための回答の型”などのスキルを教えていただいたりしました。教職実践センターの先生方に面接練習をしていただいた時には、自分の癖について知ることができました。そして、友達に面接官役をやってもらった時には、私の回答に対して、こと細かに修正をしてもらうことで回答をブラッシュアップすることができたと感じています。
作新大での学びはどのように役立ちましたか?
大学の授業では、 高浜 浩二先生の「知的障害児教育法1・2」という授業で模擬授業をたくさん行った経験が、2次試験に出題された個別対応と全体指導において役立ちました。
学外での活動では、学習塾のアルバイトで子どもたちに宿題の分からないところ等を教えていました。子どもたちとのやり取りを通して、問題の解き方を思い出すコツを身に着けることができたと思います。また、教員が実際にどのような授業や支援を行っているのかを知るために、小学校ボランティアや別室登校支援ボランティアに参加しました。ボランティアでは、学んだことを実践し、自分の支援の仕方や教え方が子どもたちにどう捉えられているかを知り、どのように改善すればよいかを考えることが多く、2次試験の対策につながりました。
後輩へのメッセージをお願いします
作新大には経験豊富な先生が多く、分からないことを懇切丁寧に教えてくださります。また、この学科では小学校一種免許状と特別支援学校教諭一種免許状(知的)を一緒に取得できることも魅力的だと思います。
福島県公立小学校合格
山内 俊太朗さん(作新学院高等学校卒業)
-
-
教員をめざすきっかけを教えてください
小学校時代の担任の先生と中学生の時の職業体験がきっかけで、教員を志すようになりました。
将来は、子どもたちが勉強ができるだけでなく、道徳心を育みながら互いを尊重し、社会に貢献できる心を育てられるような教員になりたいです。そのために、研修への参加や授業動画を見る等の教材研究を積極的に行い、学び続けていきたいと思います。
合格に向けてどのような準備をしましたか?
3年生の頃から作新大の教員採用試験講座を受講していましたが、教員採用試験に向けて本格的に勉強に取り組んだのは、4年生になる春休みの頃でした。試験勉強を始めるのがとても遅くなってしまったため、福島県の過去問を何周も解きました。その際、間違えた問題について教職実践センターの先生方に「なぜこの答えではないのか」と、自分が腑に落ちるまで、自分の考えを転換するためにたくさん質問をしていました。それによって、分からないところを“暗記”するのではなく“理解”し学習することができたと思います。
作新大での学びはどのように役立ちましたか?
4年生になる春休みにボランティア活動と教員採用試験の勉強をしていたことが合格につながったと思います。ボランティア活動では、実際に子どもたちと一緒に学習したり、休み時間に遊んだり、給食を食べたりし、その生活の中で教員を目指したいと思うようになりました。また、ボランティア活動をしていく中で湧いてきた「教員になりたい」というモチベーションを保ちながら教員採用試験に取り組むことができたため、合格につながったと思います。
後輩へのメッセージをお願いします
作新大の発達教育学科は少人数制ということもあり、分からないところや悩み等を相談しやすい環境になっていることがとても強みだと思います。また、教職実践センターには元教員だった先生方が常駐していたり、自分と同じように教員を志望している、ライバルでもあり仲間でもある学生が多数通っていたりするため、「教員になりたい」という気持ちが燃えている環境で過ごすことができます。 -